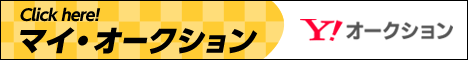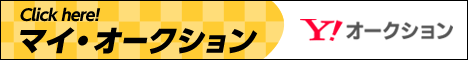| 2002年 338P 特別付録とCD-ROM付属
部数は少なそうです。資料用にもいかがでしょうか。
田沢型を中心とする富士, 風景, 旧高額, 新高額など, 大正時代から昭和初期にかけて発行された切手 は、かつて大正切手と総称されていた。これら大正切手は,現行切手として収集対象となった最初の日本切 手である。 すなわち, 1924年(大正13), 関東大震災の災害から印刷局が復興した直後、製造発売された田 沢型旧大正毛紙と富士鹿第1次旧版の耳紙には枠線がなく, 白耳であったことが、当時の収集家に大きな衝 撃を与えた。さらに,この後枠線が復活し、 銘版の表示が変わり, 位置が移されるという具合に, バラエテ ィが次々に出現したため、収集家の関心がますますたかまり,現行切手として大正切手の専門収集がはじま ったのである。 そして, 寺本義雄, 大柴峰吉, 柳原友治といった人たちを中心にその収集は進められたが、 収集の力点は耳紙の変化を加味した銘版バラエティに置かれていた。
このような銘版中心の現行切手収集は,昭和切手から新昭和, 産業図案へと受け継がれて行くが, 大正切手 の方は、戦中、戦後の混乱の中、 新しい現行切手の収集の影にかくれて、目立たなくなってしまった。
戦後の大正切手収集, 新しい切り口
戦後,大正切手の収集は,1950年代後半, 新しい展開を見せる。 西野茂雄氏による田沢切手の耳紙と目 打をからめた分類の究明, 魚木五夫, 荒田耕一両氏と筆者らによる, 主として使用済切手による目打調査な どがそれである。 ここから出発した大正切手の研究と収集は,さらに, 1980年代,筆者による用紙の分類, 色調の分類が加わって, 大正切手の分類は,用紙, 印面寸法, 色調, 目打, 耳紙, 銘版などの各ファクター を掛け合わせて, 綜合的に行われるようになり、その中から稀少なマテリアルの存在も数多く確認されてき て大正切手の世界の拡がりと深さが, 収集家に再認識されるようになってきた。 これは 「支那」加刷の場合 もおなじことがいえる。 銘版にだけ目が行きがちだった戦前の収集からみると、 まさに、隔世の感がある。 一方,柳原友治, 荒田耕一両氏によって研究, 収集の基礎がつくられた切手帳, 広田芳久氏によって本格 的な研究がはじまった軍事加刷なども, 用紙の分類が加味されて、一段と製造時期別の分類が正確にできる ようになった。 そして, これらの分野が収集対象に加えられることで, 大正切手の世界はさらなる拡がりを みせる。これらの研究成果は、そのまま日本切手専門カタログに反映されることとなった。
自分自身の収集
わたくしが菊, 田沢切手に興味をもちはじめたのは, 1950年頃で、使用済単片による目打の分類が収集 の第一歩であった。 1950年代は大正白紙や旧大正毛紙の目打バラエティ, たとえば, 単線12や旧大正毛紙 6銭,8銭,30銭、50銭の櫛型12×121/2を揃えることが中心で,どちらかといえば,少し突っ込んだゼネ ラル収集といった趣があった。 他方, 為替原符の払い下げから水はがししたと思われる, 大正白紙や旧大正 毛紙の耳紙付きの使用済 (中子持罫が多かった)も集めていて、これが専門収集へと進むきっかけとなった。 1970年代に入って、海外からコンディションのよい未使用が里帰りするようになるが,この頃から、未 使用の耳紙付きや銘版付きマルティプルを積極的に集めるようになった。 この間も自分なりに調査、研究し ながら収集を進めていたが, その成果として, 1980年代に入ると, 旧大正毛紙時代の用紙と色調分類, 新 大正毛紙時代の裏のりと色調の分類などが解明された。 これを自分のコレクションの組み立てに取り入れる とともに,日専の記述にも反映させるようになった。 これで, 大正切手の分類が製造時期を反映した, より 正確なものになり、収集に深みと厚みが加わったことは間違いない。
大正切手に興味を持って50年以上. 一歩また一歩と, マテリアルを積み上げ、コレクションの充実をはか ってきたが,大正切手の全体像がやっとみえてきたように思う。 やはり, コレクションの充実には時間が必 要なのである。しかし一方、いくら努力しても、収集困難なバラエティのすべてを揃えることは,個人では 不可能であろう。それほど大正 切手の世界は奥が深いといえる。
表紙小傷程度で特に目立った傷や汚れはありません519463S |